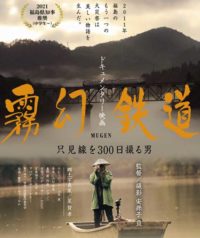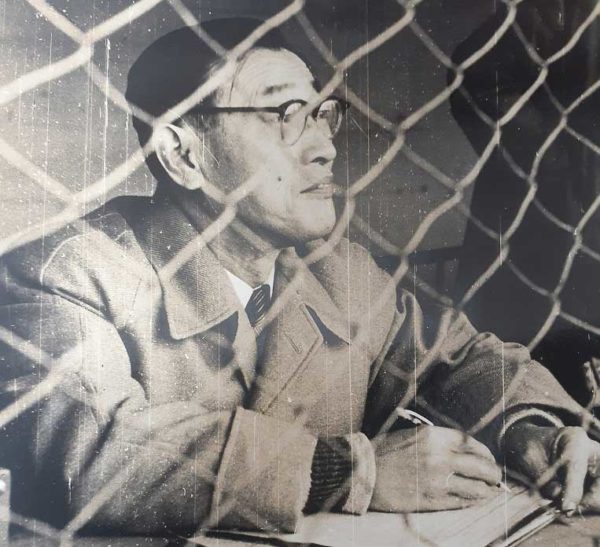ひばりタイムスは年末にニュース更新を停止します。そこで読者に加え、記事を掲載してきた「市民ライターズ倶楽部」の常連執筆メンバー13人にも同じタイトル「ひばりタイムスとわたし」で原稿をまとめてもらいました。それぞれの末尾に、推しの記事と写真を載せました。(編集長・北嶋孝)(掲載は到着順)
空き家の利活用が言われて久しいが、なかなか進んでいない。今回は、4つの空き家活用をレポートした。空き家の活用は、更地にしてアパートや貸家収入を得るのにくらべれば、手間とコストが掛かるものの、コミュニティの復活、新しい才能の開花などにとても有効だ。空き家を持て余している方、是非、一歩踏み出して欲しい。
西東京市のMUFG PARK内にある、本を持ち寄りみんなで育てる図書館「まちライブラリー」で12月15日、西東京市と小平市のがん患者支援団体が共催するイベント「本でつむぐ心のふれあいサロン@まちライブラリー」が開かれた。参加者は小説、絵本、エッセーなど、大切にしている一冊をそれぞれのエピソードとともに紹介し、本をきっかけにした新たな交流の輪が広がった。
ひばりタイムスは年内でニュース更新を停止することになりました。この最後の機会に、読者企画「ひばりタイムスとわたし」を立ち上げ、みなさんの「読者体験」を募集します。ひばりタイムスとの出会い、折に触れて読んできた記事や企画の感想、意見を聞かせていただければ幸いです。
この連載を始めたのは、2016年9月1日号。なんと足掛け8年も、書かせて頂いたことになる。この連載を終わるに辺り、自分の軌跡を整理してみたくなった。
芝久保第二運動場の年末廃止が決まり、人口20万人の西東京市の市営テニスコートは来年からわずか4面へ。近隣自治体と比べると、断トツ「ワースト1」になります。市内のコートを長年利用し、市大会でも優勝経験のある鈴木麻衣さんの危機感あふれる寄稿です。(編集部)
11月3日(文化の日)に下保谷四丁目特別緑地保全地区(旧高橋家屋敷林)にて、西東京市教育委員会社会教育課、下保谷の自然と文化を記録する会と高橋家屋敷林保存会が主催した「東京文化財ウイーク2023 第14回 屋敷林企画 保谷のアイ」が開催されました。11月にしては季節外れの暑さの下で、10時の開門時には列をなし、最終的にカウントされた入場者数は435人。多彩な催し物を家族、友人らと共に楽しんでいました。
1.定住社会から移動社会へ
自治会、コミュニティセンター、地域の居場所…と、ここ数年地べたに這いつくばるような仕事をしてきた私にとって、「デジタルノマド」が国の施策として取り上げられていることを知って、驚いた。
小平市の新しい教育委員にFC 東京などで活躍した元サッカー選手の吉本一謙(かずのり)さん(35)が就任することになり、9月29日の市議会9月定例会最終日の冒頭、登壇した吉本さんが「身が引き締まる思い。小平と社会のために貢献できるよう誠意をもって務めさせていただきます」と就任のあいさつをした。任期は10月1日から4年間。
多摩地域の地下水から発がん性の疑いがある有機フッ素化合物(PFAS=ピーファス)が高濃度で検出され、市民の不安が広がっています。東京都は多摩地域の一部井戸の利用を中止し、独自の対策に乗り出す自治体も出ています。そもそもPFASはなぜ多摩地区の水源となる井戸に混入したのでしょうか。災害対策として井戸の調査・普及に努めてきた市民団体「小平井戸の会」代表の金子尚史さん(80)の寄稿を掲載します。(編集部)
歩きながら地域の魅力を実感できるイベント「西東京シティロゲイン2023」が11月19日、西東京市で開かれる。その土地の人気スポットや名所旧跡などを制限時間内に回って得点を競うスポーツ。その魅力を知る市内在住・在勤のメンバーらが実行委員会を作り、西東京市の後援も得て、このエリアで初の企画に取り組んだ。
敗戦前後から北多摩の歩みをたどってきた連載企画「北多摩戦後クロニクル」は前回で1980年代に入った。当時、この地域はどんな表情を見せていたのか。写真家の飯島幸永さんは長く武蔵野に暮らしながら「風土と人間」をテーマに作品を撮り続けてきた。今回は「写真特集」として、1981(昭和56)年を中心に武蔵野の四季と人々の営みを捉えた飯島さんの写真とエッセーをお届けする。(編集部)
最近の集中豪雨で鉄道の被害も伝わってきます。JR只見線もかつて大きな被害を受けながら、10年余りかけて昨年10月に全線開通しました。その経緯をたどるドキュメンタリー映画「霧幻鉄道」が9月中旬、東久留米市「まろにえホール」で上映されます。近隣3市の福島県人会(東久留米、小平、西東京市)の共催。その一つ、西東京福島県人会の管敏二さんの報告です。(編集部)
今年の夏も高校野球にプロ野球、都市対抗野球と、野球のトピックは途切れません。野球の話で盛り上がる時、あるいは往年の選手のすごさを想像する時に、「記録」を切り口にすることは結構あるのではないでしょうか。