小平霊園・著名人の墓巡り(上)
子どもに歌や物語を送った文化人
今年のお彼岸は3月17日から23日まで。この時期、東京都小平霊園には1日数万人の墓参者が訪れるというが、今年は新型コロナウイルスの影響でどうなるか。イベントや行事が次々に中止となり、各種施設も閉館・休業が続く日々。自宅で鬱々としていても仕方がない。自然豊かな霊園内は散歩や花見のスポットとして親しまれ、多くの文化人や政治家が眠っていることでも知られる。早春のうららかな午後、気分転換に著名人のお墓を訪ねて霊園を散策してみた。
1948年に開園した小平霊園は東村山市、小平市、東久留米市にまたがり、広さは約65万平方メートルと東京ドーム14個分に相当する。その半分は一般墓地や芝生墓地などの墓所が占め、残り半分は武蔵野の風土を残した樹林や緑地、園路が広がる。
西武新宿線小平駅の北口から線路沿いにケヤキ並木の表参道を歩くと、ほどなく正門に着いた。右手に梅林が見え、アカマツが並ぶ幅約50メートル、長さ約600メートルの中央参道の両翼に一般墓地が広がっている。
入り口の管理事務所でもらった案内図には「著名人墓地」として48人の名前と肩書、墓の場所が記されている。事前に下調べはしてきたが、これを頼りに歩くことにした。
目当ての一つは、民衆の工芸品に美を見出す民芸運動の提唱者、柳宗悦(1889〜1961年)の墓だ。梅の木の下に立つモダンな五輪塔は表面を粗面のノミ切り仕上げにして手仕事の素朴な質感を出している。日本のインダストリアルデザインを確立した長男の柳宗理(1915〜2011年)による意匠で、宗理自身ここに埋葬されている。
もう一つ確かめたかったのが、「七つの子」「シャボン玉」などの童謡を残した詩人、野口雨情(1882〜1945年)の墓だ。この墓にちなんで、毎年5月にルネこだいら(小平市民文化会館)で「こだいら雨情うたまつり」が開かれている。墓石には本名の「野口英吉」「妻つる」と並んで大書され、花が供えられていた。
ウェブサイト「文学者掃苔録」によると、生地の茨城県北茨城市にある野口の墓は先妻の長男が建て、「野口雨情墓」と記されている。小平霊園の墓は再婚相手つるとの間に生まれた三男の手で建てられた。墓石の文字に遺族の思いがにじむ。
子どもに向けた作品を世に送り出した作家では雨情のほか、映画化もされた小説『二十四の瞳』の作者、壺井栄(1899〜1967年)、童話『赤い蝋燭と人魚』で知られる小川未明(1882〜1961年)が眠る。
案内図には記されていないが、目に止まったのが戦後に童謡「小鹿のバンビ」を大ヒットさせた歌手、古賀さと子(1940〜1996年)の墓だ。傍らに「古賀さと子の思い出」と記した抽象彫刻が置かれ、「田原総一朗書」とある。古賀の姉はジャーナリスト田原の妻でエッセイストの田原節子(1936〜2004年)。彼女もここに埋葬されていた。墓参りにはこうした意外な発見もある。
子どもとの関連で言えば、南口近くに「子どもの碑」(1951年建立)がある。児童福祉施設で亡くなった身寄りのない子どもの遺骨97柱を収めており、毎年11月に慰霊祭が行われている。墓誌に刻まれた名前のうち2人分が消されていた。都によれば、のちに身寄りが見つかって遺骨が引き取られたとのことだった。
(片岡義博)(写真は筆者撮影) >> 【下】墓石が映し出す時代と社会(3月10日掲載)
【関連情報】
・小平霊園(都立公園公式サイト・TOKYO霊園さんぽ)
・ウェブサイト「文学者掃苔録」
(一部が大塚英良著『文学者掃苔録図書館』として刊行)
・子どもの碑(東京都福祉保健局)
- 地域報道サイト「はなこタイムス」が新年開設 北多摩北部のニュースを掲載 コミュニティーFMくるめラ社長が運営 - 2023年12月25日
- 「担任教諭と同級生のいじめで不登校に」 いじめ重大事態の児童側、小平市を提訴 市議会で市長が報告 - 2023年11月28日
- 小平市が第3子以降の給食費を無償化 来年1月~3月分を補正予算案に盛り込む - 2023年11月24日









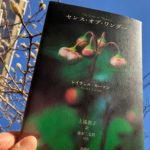



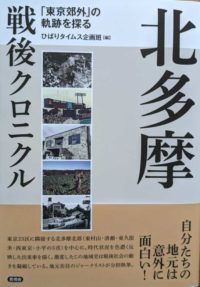














曖昧な記憶ですみませんが、黒目川の源流がこの霊園内にありませんか?
はい、あります。「さいかち窪」と呼ばれ、大雨後に湧水がたまるようです。(下)に写真で登場します。