写真で見るお正月 自宅で外で迎える風景
2019年、平成31年。5月から新元号に変わる今年。平成最後のお正月。とは言っても、過ごし方は人さまざま。自宅に籠もったり外出したり…。ひばりタイムスに執筆している方々を中心に、写真と文で綴ったそれぞれのお正月-。(編集部)
国や地域によって、西暦の1月1日が新年とは限らないけれど、少なくとも日本は暦の上で新しい年を迎えた。参拝客がひきもきらない神社とお寺はお正月の定番風景だ。希望、願い、祈り。リアルは想像できる。だからこそ、年の初めぐらいは夢を招きたい。

飯盛山(はんじょうざん)仁王院鎖大師 青蓮寺(しょうれんじ) 元旦の朝 9時、車で鎌倉の夫の実家に行った。いつもこのくらいの時間は、まだ道路は空いている。鎌倉山に入る手前のお寺で、鐘を撞くことができた。鐘のそばには、「鐘をつく皆さんへ」とご住職から、お作法の案内が書かれていた。先客の後ろ姿を撮らせてもらった後、私も早速「南無大師遍照金剛」と唱えて撞いてみた。ひいたおみくじは、娘とともに大吉だった(石田裕子)
太陽はどこから見ても太陽に変わりはないはずだが、やはり違う。日の出、日の入りの違いもあれば、状況の変化によって、まったく別の姿を見せる。

「初日の入り」(1日午後4時28分、小平市内のマンション5階から)。今年の元旦はよく晴れて、初日の出だけではなく、初日の入りもきれいだった。マンション上階の廊下では、しばらく眺める家族やカメラを構えるお父さんの姿も見られた。富士山、太陽、空、雲が織りなす夕景。古代の人たちも同じような気持ちで眺めていたのだろうか(片岡義博)
海、山、町場。昼と夜。お正月の風景は賑わいと静かなたたずまいが交錯する。まあ、ご覧あれ。

2日午前、都立小金井公園内にある「江戸東京たてもの園」で獅子舞が奉納された。昭和初めの銭湯を復元した「子宝湯」の前、人垣が幾重に取り囲む中で笛と太鼓の音(ね)に合わせて緩急つけた舞を披露。その後、「獅子が頭を噛んで悪い虫を食べます」と子どもたちの頭を獅子頭で噛んで回った。ご利益にあずかろうとする親子連れが押し寄せ、ひしめき合った(片岡義博)
(川地素睿、石田裕子、卯野右子、片岡義博、北嶋孝)













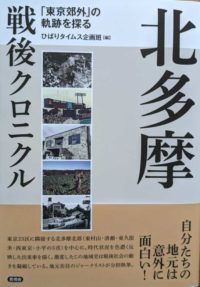














面白い企画でよいと思います(^o^) いろいろなお正月があるのですね。大根の子が可愛い。子どもの写真を使いたくても、なかなか使えないなか、家族だからこそでしょうか。