
書物でめぐる武蔵野 第21回 その昔、「三多摩」は神奈川県だった
昔といっても、明治初期のこと。いわゆる三多摩地区は神奈川県に属していたことがあった。その後はずっと「東京」に帰属するが、この歴史は、多摩地区の微妙な位置をあらわしているのかもしれない。
(写真は、ひばりヶ丘駅に入線した東急東横線の車両。「神奈川県」は意外に近い)
小説『武蔵野インディアン』
『武蔵野インディアン』という小説作品があることをご存知だろうか。書いた作家は三浦朱門。文壇的には「第三の新人」に括られるが、夫人が曽野綾子で、文化庁長官(中曽根内閣)になった作家という印象のほうが強い(筆者の個人的な感想です)。
この作品は、作者が多分に投影された「佐野」を主人公とする4つの連作で構成されている。作家である佐野が、戦中から戦後にかけての武蔵野≒多摩地区での生活を、その時代の友人たちと再会しながら回顧し、作品が発表された81年当時の武蔵野についてもふれている。時代をまたいで変貌する武蔵野の風俗を知ることができる〝武蔵野小説〟といっていいだろう。
気になるのは、もちろんタイトルとなっている「武蔵野インディアン」だ。「インディアン」という言葉は、子ども時代に西部劇を見た人間にとっては、「悪者」の代名詞として認識されている。やがてそれは、アングロサクソンがアメリカ大陸を先住民から略奪した際のもののいいであることを知った。そもそもアメリカの先住民を「インディアン=インドの人」という誤った認識で(新大陸「発見」のときの誤解)呼ぶことじたいナンセンスである。最近では「ネイティブアメリカン」という呼称が一般的になっている。
脱線するが、アメリカのメジャーリーグ・ベースボールのチーム名に、去年まで「インディアンス」があった。日本でもヒットした映画『メジャーリーグ』(89年)のモデルとなっていたし、「インディアンス」は蔑称とはとらえられていないのではないのかと思っていた。ところが、昨年(2021)このチームは、「インディアンス」は差別的であるという批判を受け、改名することを発表し、今年から「ガーディアンズ(Guardians)」を名乗っている。
名前を変えることで差別はなくならないと思うし、中米では同じ語源の「インディオ」という呼称は問題なく使われているようだ。言葉の言い換えにはモヤモヤ感が漂うが、これ以上は踏み込むことは控える。*yahooの阿佐智の記事を参照した。
武蔵野ネイティブ
本家がそういうことになっているせいではないと思うが、『武蔵野インディアン』(河出書房新社)は現在品切れで、読むには古書店や図書館を利用するしかない。この作品が発表されたのは前述のように1981年。その頃、「インディアン」について現在のような微妙な感触は、作者にも読者にもなかったと記憶する。
では、武蔵野の「インディアン」とはどういう人たちを指すのか。
それは東京以前から「先祖代々」(連作の1作目はこのタイトルになっている)この多摩地区に住み続けている人びとのことだ。主人公は子どものときこの地に住んでいたことがあるが、地元民ではなく新参者という設定。時代を経て作品中で再会する旧制中学時代の友人たちが「ネイティブ」であり、彼らは自らを「東京白人」に侵略された「武蔵野インディアン」と称している。
彼らからすれば、都心との交通よりも、横浜へ生糸を運んだ「シルクロード」である鎌倉街道のほうが重要だったし、新選組も明治の自由民権運動もネイティブの抵抗運動だったということになる。この認識は、都心と多摩地区(武蔵野)の決してフラットではない関係を、率直にあらわしていると思う。
主人公は、酒場で再会したネイティブの友人たちに、どうして自分のような「東京白人」にご馳走するんだ、と問うと、友人たちは(作家になった)主人公に「われわれの声を代弁してほしいのさ」と答え、さらに続ける。
《「おい、日清戦争の前の年まで、今の東京都下は神奈川県だったのを知っているか。都内に対して都外というならわかる。都の外だから、なら、多摩県でもいい、神奈川県でもいい。しかし、都下という言い方、いかにも東京白人の発想だ。植民地扱いじゃないか」》p97
なるほど、地元の人はそんな思いで、東京と武蔵野の関係を見ていたのか、ということがわかる。
この作品の存在を教えてくれたのは、何度も引用している川本三郎の『郊外の文学誌』だ。川本はこの作品を「多摩のネイティブから見れば、自分たちは、しょせん、新しく進入してきた東京白人に過ぎないという、視点の変換を獲得した」と評価している。(P310)
たしかに、「武蔵野インディアン」というのは東京を相対化する視点だし、意表をつく表現だが、いかにも〝酒場の話題〟だという気がしないでもない。
神奈川県と東京府の綱引き
先の引用中、「都下は神奈川県だった」という発言がある。冒頭でも述べたように、三多摩は神奈川県だったことがある。「そっちのほうがよかったな」と思った人がいるかもしれないが、そのへんの意識は多摩の〝自虐意識〟とつながってくる。
三多摩地区*は、明治11(1878)年の郡区町村編制法によって、神奈川県に編入されている。これに対して、東京府は明治10年代、江戸時代から東京の「水がめ」である三多摩を東京に編入しようと画策していたようだ。しかし、これは神奈川県に反対されて、実現しなかった。
局面が変わったのは、明治22(1889)年、甲武鉄道(現在のJR中央線)が新宿から八王子まで開通したときだった。これをきっかけにして、明治26(1893)年、三多摩を東京府に編入する法律案が帝国議会に提出され、僅差で可決成立、同年4月1日、三多摩地区は東京府に編入されたのである。
(国立公文書館のサイト「変貌―江戸から帝都そして首都へ」を参照した)
* 三多摩に属していた主な地域(現在の名称)
北多摩郡:武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、狛江市、小金井市、国分寺市、国立市、立川市、昭島市、西東京市、東久留米市、清瀬市、東村山市、小平市、東大和市、武蔵村山市、および世田谷区の一部
南多摩郡:八王子市、日野市、町田市、稲城市、多摩市
西多摩郡:あきる野市、青梅市、福生市、羽村市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、桧原村
ただし、別の本**のよると、東京への移管が決まった1890年代、多摩地区じたいもこの問題で「大揺れにゆれる」状態だったようだ。三多摩内部では、神奈川につきたい南多摩・西多摩のほうが、東京がいいという北多摩より優勢だったが、衆議院では逆の結果となった。ということもあり、この火種はくすぶり続け、移管のわずか3年後、今度は明治政府が「多摩を都制から除外し、東京市に隣接する五郡とともに「武蔵県」にするという案」を出すなど、結局1943(昭和18)年の都制施行までこの争いは続いたようだ。(P256)
** 新井勝紘、松本三喜夫編『多摩と甲州道中』2003年、吉川弘文館
さらに注釈
このことを調べていると、「北多摩」は一筋縄ではいかないことがわかった。「世田谷」もその一部だったこともあるようだし、いろいろな出入りが認められる。なかでも意外なのは、「保谷村」が北多摩ではなかった時期があったことだ。
《一八七一年(明治四)一一月に品川県が廃止されると、田無村は入間県の管轄となったが、翌年一月二九日には神奈川県に編入されなおした。これ以後、九三年(明治二六)の東京移管まで、多摩の村々は神奈川県の管轄となった。ただし、現在の中野・杉並などは東京府に編入され、また保谷三カ村は入間県に残り、一九〇七年(明治四〇)まで埼玉県に属した。》(『田無市史』第三巻通史編 p659、下線は引用者)
明治初期にはいろいろな県があったことがわかる。保谷村は神奈川県に入ったことはなく、隣の久留米村などが東京府になっても、埼玉県に属していた時代があったというのは、なかなか興味深い。
「都下」という意識
そういう歴史があったためか、〝東京なのに東京ではない〟三多摩の住民は、自らの居住地を「都下」と呼ぶようになった。これは実際に筆者の親もそう書いていたような記憶があるし、『武蔵野インディアン』でもみたとおりだ。なにしろ都の「下」なのだから、自虐的と言わざるをえない。
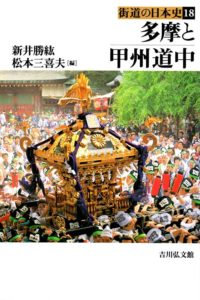
『多摩と甲州道中』(Amazon)
『多摩と甲州道中』も「「都下」と使う場面では、都に対して卑下した感覚があることはどうしてもぬぐえない」と述べている。さらに「戦後長い間「三多摩格差」という言葉が、多くの人びとの口から発せられた」としている(p258 執筆は新井勝紘)。
「都下」という言葉は死語に近くなり、格差は「三多摩」(これも死語?)の問題というより、日本社会全体を覆う問題となっている。しかし、土地をめぐる微妙な意識は、いまも存在している。「たしかに区部より旧三多摩は田舎だよな」という漠然とした意識がそれだ。
が、それはただのイメージではなく、数値としても裏付けられている。「公示地価」とか「路線価」といった「地価」がそれだ。この世界には、間違いなく土地についてのヒエラルキーがある。たとえば〝高級住宅地〟を比較する場合、東久留米市の〇〇町よりも港区の△△町のほうが上になるだろう。つまり「価値が高い」ということだ。
土地の売買や資産の計算上のこの「価値観」は独り歩きする。土地の「ブランドイメージ」はここから形成されていると思われるし、土地のステータスに自分を重ねるというのは、この「価値観」にどっぷりとハマっている証左といえるだろう。とはいうものの、この価値観と無縁な現代日本人はいないのではないか。
そういう価値観をもたらしたのは、戦後の高度経済成長であり、その後現在も続く都市化の流れであるのは間違いないと思う。
「多摩人」
『多摩と甲州道中』はこんな言い方をしている。
《高度経済成長にともなっての日本列島改造論が、大手を振って多摩の丘陵地にも押し寄せ、巨大住宅団地建設のための開発と造成が赤土をむき出し、自然を破壊し尽くし、自然と共生してきた多摩人の心身に土地代金という札束と共に大きな影響を与えたのである。》p258 下線は引用者
ここでの「多摩人」は、「自然と共生してきた」ということから、「武蔵野インディアン」とほぼ等しいといえるだろう。その意味での「多摩人」は戦後から続く圧倒的な都市化の波に飲み込まれ、姿を消している。
ただ、「多摩人」はもう少し広い概念のようにもみえる。現在「多摩人」が存在するならば、それは圧倒的な「新参者」によって構成されなければならないだろう。しかし、「多摩人」という意識を、多摩に住む人びと、つまり我々は持っているだろうか?
東京に対抗する「多摩」という二項対立で考えられるほど、東京は単純じゃない。都市化の流れを押しとどめ、かつてあったという「自然との共生」を復活させましょう、というかたちで「多摩」や「多摩人」を考えることができるのだろうか。夏休みの宿題が出てしまった。
*連載のバックナンバーはこちら⇒
- 書物でめぐる武蔵野 第36回(最終回)
西武池袋線で悪かったな 武蔵野「散歩」主義の試み - 2023年12月28日 - 北多摩戦後クロニクル 第48回
2021年 東久留米駅西口に「ブラック・ジャック」像設置 マンガやアニメでまちおこし - 2023年12月5日 - 書物でめぐる武蔵野 第35回
東久留米の水辺に古代人 身近に潜む意外な「物語」 - 2023年11月23日























