北多摩戦後クロニクル 第28回
1974年 小平・鈴木遺跡発掘 日本有数、旧石器の宝庫
1974(昭和49)年、小平市立鈴木小学校の建設現場から後期旧石器時代の大遺跡が見つかった。戦前まで日本には旧石器遺跡はないと考えられていたが1946年、群馬県で岩宿遺跡が発見されて以来全国で発掘が相次ぎ、そのうち鈴木遺跡は総面積23万平方メートルに及ぶ規模の大きさ、遺跡が示す年代の長さ、石器の豊富さなどで有数とされる。
■ 偶然の発見から大遺跡が
もともと武蔵野台地は自然の川が少ない上、近世以降の土地利用による変化が激しく、特に戦後は住宅地化が進んだことから、大規模な発掘成果はそれほど期待されていなかった。
74年6月、小平市鈴木町の鈴木小学校建設現場で偶然江戸時代の水車跡が見つかったため専門家に相談。以前に付近で石器が出土し「回田(めぐりた)遺跡」と呼ばれていたことから念のため試掘が行われた結果、遺跡の存在が確認され、本調査に移行した。
この調査によって、この遺跡が予想をはるかに超えた大規模で内容豊かな後期旧石器時代の大遺跡であることが確認され、あらためて「鈴木遺跡」と名付けられた。2019年までの45年間にのべ80カ所以上で発掘調査が行われ、石器だけでも4万点以上出土するなどの発掘成果が積み重ねられた。
日本の旧石器時代は縄文時代に先立つ3万8千年前から1万6千年前までの約2万2千年間続いたと考えられている。鈴木遺跡の場所は現代の石神井川の水源を取り囲むように位置しており、当時の寒冷な気候の中で人々の生活、食糧確保、交流などに適した環境が長期にわたって保たれていた。
鈴木遺跡発掘調査の結果、関東ローム層最上層の旧石器時代の堆積からさまざまな石器が出土した。特に打製や、刃に当たる部分を研いで鋭くした局部磨製の石斧(せきふ)類が代表的で、石斧は全国的にも出土例が少ないにもかかわらず鈴木遺跡では22点も見つかっている。
また、割れ口が鋭くナイフやかみそりのような刃物として使える石器の材料となる黒曜石が大量に見つかったことも特徴の一つ。化学的調査から材料原産地が長野県、静岡県、栃木県のほか遠く海を隔てた伊豆諸島・神津島にも及んでいることが分かった。石器材料の集散、交易、加工の地としての役割が大きかったことが考えられる。
■ 広大な遺跡保存区を計画
小平市鈴木遺跡資料館によると、旧石器時代のこの地域は水が得られる貴重な場所としてさまざまなグループの人々が生活し、物資の集散、交流などのセンターのようなイメージだったと想像されるが、定住した痕跡は見つかっていない。大型動物の捕獲、解体処理、調理が盛んに行われたことも石器の種類から推定される。そのような営みが2万年以上にわたり連綿と続いたことを明確にたどることができるのも他の国内の旧石器遺跡に見られない特徴になっている。
旧石器時代に続く縄文時代に入ると、鈴木遺跡では少数の土器片、石器などは出土するものの竪穴住居などの居住痕跡は見つかっていない。石神井川の水源が東に移動し環境が変化したためだと考えられている。ずっと後の江戸時代になって水利施設が整備されるまで、この地は人の居住に適さなかったらしい。しかし、イノシシやシカを捕らえるための落とし穴跡などが見つかっており、狩り場として盛んに利用されていたことを物語っている。
鈴木遺跡は2012年3月、東京都指定史跡となり、21年3月には国の史跡に指定された。これを受けて小平市は史跡保存の取り組みを進めている。遺跡の中心部に当たる広大な敷地にはもともと農林中央金庫小金井研修所があり、研修所の廃止に伴い売却と宅地開発が計画されていた。
遺跡保存の観点から粘り強い交渉が進められた結果、旧石器が濃密に埋蔵されていることが予測される北半分の用地が市に寄贈された。今後数年をかけて遺跡保存区として整備する計画だ。今後発掘技術が進歩した上で調査が再開されればまた驚くような発見があるかもしれない。
■ 石神井川がはぐくんだ生活と文化
北多摩の遺跡調査と保存は急速な都市化、宅地化や予算不足と闘いながら進められてきたのが実情だったが、近年になって地元の貴重な文化、教育、観光資源として積極的に整備・活用する機運が生まれた。
その中で、小平市を水源とする石神井川は武蔵野台地を流れる数少ない自然河川として人々の生活、文化と歴史をはぐくみ続けた。鈴木遺跡の東約5キロ、西東京市では以前から約5千年前から4千年前の縄文中期の環状集落を最大の特徴とする遺跡が発見されており、1973年からの本格調査で下野谷(したのや)遺跡と名付けられた。流域の拠点集落として、南関東で傑出した規模と内容を誇っている。
下野谷遺跡も2007年に一部公有地化して縄文住居などを再現した公園を整備、地下の遺跡は保護されて15年には国の史跡となった。西東京市は毎年、縄文体験ができるイベントを実施するなどして普及に努めている。
石神井川流域にはここから下流側にも豊かな遺跡群が広がっており、今後、遺跡の一体的調査や研究交流の発展も期待される。
(飯岡志郎)
*連載企画「北多摩戦後クロニクル」の >> 目次ページへ
【主な参考資料】
・小平市教育委員会編『旧石器時代の鈴木遺跡』(2021)
・日本列島の旧石器時代遺跡(日本旧石器学会)
・鈴木遺跡の「発見」(小平市)
・下野谷遺跡(西東京市)
- 北多摩戦後クロニクル 第50回(最終回)
2022年 多摩モノレール延伸計画発表 東西を貫く交通インフラ完成へ - 2023年12月19日 - 北多摩戦後クロニクル 第42回
2002年 早大ラグビー部が「さらば東伏見」 74年の歴史に幕、今も学生スポーツの聖地 - 2023年10月24日 - 北多摩戦後クロニクル 第39回
1995年 東村山で下宅部遺跡発見 縄文人が極めた漆工芸の技 - 2023年10月3日











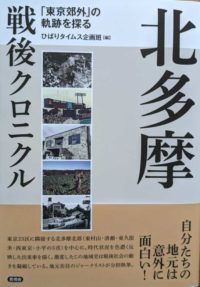














私の場合、鈴木遺跡よりも鈴木小学校が出来た過程の方が思い出深いです。鈴木遺跡の近くの第8小学校には竪穴住居があったからね。鈴木小学校は戦後のベビーブームで第9小学校の校舎が足りなくなった為、分校という形で出来たからね。懐かしい話です。