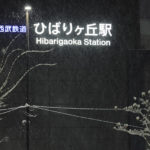書物でめぐる武蔵野 第25回 もしも「ひばりヶ丘」が「自由学園前」だったら―学園都市の夢想
原武史著『レッドアローとスターハウス もうひとつの戦後思想史』(新潮社)の〝主役〟は「ひばりが丘」である、といいたい。16本ある章題のうち6箇所も「ひばりが丘」(1箇所は駅名の「ひばりヶ丘」だが)が出てくる。かつて、こんなボリュームで「ひばりが丘」を取り上げた本は、たぶんなかった。(写真は「ひばりヶ丘パークヒルズ管理サービス事務所」として残されたひばりが丘団地の「スターハウス」)
「レッドアロー」と「スターハウス」を説明しておこう
念のために書くが、「ひばりが丘」は本サイト「ひばりタイムス」の名前の由来となっている西武池袋線ひばりヶ丘駅周辺の地域を指す。「ひばりが丘」は北海道の札幌市内にも存在することを、筆者は路線検索で知ったが、知り合いの間でそれが話題になったことはない。東京在住以外の人に(東京の人でもけっこうしばしばあるが)、この地を説明するときは、「池袋は知ってますよね? 所沢はわかります? その中間くらいにあるところです」と話す。それくらいの知名度ということだ。
「ひばりが丘」の名が全国的に広まった出来事があった。ある年齢以上の人にそのことを話せば、だいたい「ああ、あそこ」ということになるが、その出来事については、あらためて述べる。

『レッドアローとスターハウス』書影
書名にある「レッドアロー」というのは、西武池袋線が秩父まで延長された1969年、同じタイミングで登場した、西武鉄道初の座席指定の特急列車。この本で扱われる西武鉄道の、さらには「西武的なるもの」の象徴という意味がある。
もうひとつの「スターハウス」は、ひばりが丘団地にあった「星形住宅」の別名。箱型スタイルでないところが特徴的で人気があり、この建物に入居するのは難しかったそうだ。ひばりが丘団地の象徴であり、「団地時代の幕開けを告げる記念碑的建物」(p27)ということができる。
この「西武的なるもの」と団地という特異な住空間がむすびついて、60年代から70年代半ばにかけて、西武池袋線周辺に独特な政治風土を生んだ。端的には70年代の日本共産党の〝躍進〟に、西武鉄道沿線に多数存在した団地が大きく寄与したことを指している。
その時代の政治思想というと、全共闘運動や連合赤軍事件といった「新左翼」系についての議論が多いが、既成左翼政党の支持基盤の形成やその盛衰について語られることはあまりなかった(日本共産党が自らのことをそのように語るわけがない) 。その意味で「もうひとつの戦後思想史」というのが、書名が意味するところである。
「西武沿線住民」意識

『滝山コミューン 一九七四』の書影
著者の原武史は、日本政治思想史を専門とする歴史家で、近代の天皇や鉄道についての仕事が多い。幼少期、ひばりが丘団地、久米川団地、滝山団地という西武沿線の公団団地で13年間過ごしたという(p30)。その滝山団地の小学校で受けた強烈な「集団主義(平等を標榜した全体主義)教育」体験をレポートし、検証したのが、講談社ノンフィクション賞を受賞した同著者の『滝山コミューン 一九七四』(2007年、講談社)である。『レッドアローとスターハウス』は『滝山…』の続編と位置づけられる。
著者は、その「集団主義」の淵源を考えたに違いない。それは主導した教師の独創ではなく、団地という環境が、逸脱を許さず均質化を強要する傾向を助長したと考えただろう。
では、団地とはどういう空間なのか? それはただの住まいの器ではなく、その住民のさまざまな意識を規定している。すると、「滝山団地」の近隣にあり、団地としては〝先輩〟で、戦後の団地を代表する「ひばりが丘団地」を調べてみなければならない。そう考えたのではないか。このようにして本書の〝主役〟ひばりが丘(団地)が浮上する。
さらに、この団地という文化は、西武鉄道と密接にむすびついていることに思い至ったのだろう。そこで西武鉄道と西武沿線の歴史について、歴史家らしい豊富な資料にもとづく分析が展開されることになる。
《(西武)池袋線と新宿線にはさまれた区域では、鉄道やバスはもとより、百貨店やスーパー、遊園地など娯楽施設に至るまで、堤康次郎を総帥とする西武資本による一元支配が貫かれた。「練馬区民」「所沢市民」といった行政区分よりもっと強い、「西武沿線住民」という意識がつくられてゆくのである。》p8
そして、この地域に日本住宅公団によってひばりが丘団地や滝山団地が建設され、「西武沿線住民」意識はさらに強められたとする。
ひばりが丘=学園都市の可能性
たしかに、団地なしには「ひばりヶ丘駅」自体、成り立たない。そもそも「ひばりヶ丘」という名前で、駅が誕生したわけではないのだ。
この駅の前身は「田無町」という名前だった。1924 (大正13)年の開業。この路線のオリジナルメンバーである「保谷」や「東久留米」ができたのは1915(大正4)年だから、新参者である。当時の「保谷村」につくられたのに、この地域の中心だった「田無町」の地主などの要請でこの名になったようだ(この事情は萩原恵子・松田宗男「武蔵野鉄道が通る!」による)。
駅開業の翌年、自由学園の一部施設がこの地に移転してきた(34年に完全移転)。自由学園は土地を分譲して学校運営の資金にしたという。つまり学園がまちづくりをしたことになる。「田無町」は自由学園のための駅みたいになった、と想像される。
ならば、小田急の「成城学園前」のように、「自由学園前」に改称する可能性はなかったのか? 成城の場合は学園が鉄道に働きかけたようだが、自由学園が改称を働きかけた「形跡」はない(『レッドアローと…』p35)。
これはとても残念なことではないだろうか。時代は下って昭和期のひばりが丘地区には、自由学園(最高学部)、明治薬科大学(98年清瀬に移転)、武蔵野女子大学(現在・武蔵野大学)という〝大学〟が3つもあった(いまも2つあるけど)。にもかかわらず、いまも昔も、大学が3つある江古田のような学生街という感じも、国立のような学園都市という感じもまったくしない。潜在力はあるにもかかわらず、である。まちの魅力ということを考えると、残念といわざるをえない。
ひばりが丘は学園都市を目指したわけではないかもしれないが、そういう選択肢がなかったわけではないのだ。自由学園が土地を分譲していたころ、箱根土地株式会社(西武HDの前身企業)は大泉を学園都市にしようとしていた。しかし、東京商科大学(現在の一橋大学)に逃げられ、大泉は名前だけの「学園都市」となる。箱根土地は、小平でも学園都市構想に失敗したものの、結果的には国立を学園都市として開発することになった*。
この状況からすると、ひばりが丘が自由学園を中心とした学園都市になっていても不思議ではなかった。そうならなかったのは、戦前から戦後にかけての自由学園と〝西武〟の、そして戦後の住宅公団、それぞれの思惑があった。そこに住民の無意識が加わって、ひばりが丘は、「リビングタウン」ではなく、団地のまち「ベッドタウン」を選んだのである。
最近、「ベッドタウンからリビングタウンへ」というコンセプトで、西武HDと住友商事が共同で所沢の西口を再開発しようとしている記事がひばりタイムスに載った。(10月29日掲載「『ベッドタウンからリビングタウンへ』 所沢駅西口に広域集客型商業施設、2年後オープン」)
21世紀になってやっと西武沿線は「ベッドタウン」を〝卒業〟するのだろうか。
*西武の土地開発についてはこの 連載13 の「大泉学園」のところで、西武鉄道が他の私鉄を買収して増殖してきた歴史については 連載2 でふれている。
「ひばりが丘団地」の誕生
さて、話を太平洋戦争を経た1950年代末に戻そう。経済成長にともなう住宅不足を解消するため、55年に日本住宅公団が発足すると、公団は東京の郊外に次々とコンクリート製の大規模な集合住宅を建設していった。とりわけ西武鉄道沿線には集中的に団地が建てられた。『レッドアローと…』の原武史は、東急が田園都市線沿線に一戸建てを中心にした「東急的郊外」をつくったのに対し、団地を主体とする「西武的郊外」と呼んでいる(p117)。その代表が59年に生まれた「ひばりが丘団地」なのである。
都心からそこそこ離れているのが都合よかったせいで、郊外には巨大な軍事施設*の跡地があり、駅のすぐそばは雑木林と畑、つまりほとんど田舎という環境は、集合住宅を建てるのにもってこいだったのだろう(*ひばりが丘団地は中島航空金属 田無製造所の跡地につくられた)。
ただ、西武は鉄道と一体化した住宅開発に熱心ではなく、公団がその「肩代わり」で大規模集合住宅をつくっていった(同p147)。だから駅から近くはない畑の真ん中に、突然団地が出現したというわけだ。
「ひばりが丘団地」は、当時日本最大の規模と最高の環境と内容を誇ると喧伝され、外国人の関心も集め、多くの大使などが訪れたようだ(p163)。
そして団地の誕生と時を同じくして、59年5月「田無町」駅は「ひばりヶ丘」と改称された。西武と公団の思惑が合致した結果といえよう。
アメリカ的というより旧ソ連的
「ひばりが丘」の名を全国に広めた出来事とはなにか。それは、60年9月、前年結婚した皇太子夫妻が「ひばりが丘団地」を視察したことを指す。ダイニングキッチンや浴室がある近代的な住居に核家族が住むという団地の生活。団地はそれまでのアパートや貸家とは違った新しい時代の暮らしを提供する場所であり、皇太子夫妻の団地訪問はそうした生活に〝お墨付き〟を与える象徴的な役割を果たしたといえるだろう。
団地ライフが憧れだった時代があったということだ。60年代、団地はどんどん増殖していった。この流れを日本社会の「団地化」と呼び、それは地域共同体の空洞化であり、現在の社会全体の空洞化につながる「郊外化」の第一ステージととらえる考え方がある(宮台真司『経営リーダーのための社会システム論』連載23を参照)。
これに対して原武史は、団地自体の共同性に注目している。団地の生活は、たしかにそれまでと比べればプライバシーも守られ、アメリカナイズされた側面もある。しかし、みんな同じような暮らしをせざるをえないというその均一性、画一性は、同時代の旧ソ連など社会主義国の集合住宅とそっくりであることを強調している(実際に原はモスクワを取材している)。
《「個」が確立したように見えながら、そこにあるのは恐ろしく同質的な「集団」の生活であった。》p167
と述べ、長くひばりが丘団地の住民だった文芸評論家の秋山駿の言葉も引いたりしながら、「団地とコミュニズムの親和性」を指摘する。原はこれを言いたいがために、この本を書いたのかもしれない。
団地や鉄道の路線と政治意識については、次回みることにして、ちょっと言っておきたいことがある。
書店の消滅
『レッドアローとスターハウス』は2012年刊だから、出てからもう10年も経つ(2017年に増補版が出ているようだ)。
刊行当時、ひばりヶ丘駅の急な北口階段の真ん前にあった正育堂書店の入り口に、山積みになっていたことを思い出した。
この10年の間にひばりが丘は、駅周辺と団地を中心に激変したといっていいだろう。だから「いまや歩く人影すらもないひばりが丘団地の風景が、西武の現在を象徴しているように見えた」(p29)という状況も変わっている。それだけ先に挙げた日本社会の「郊外化」は進んでいるといっていいのだろう。
「郊外化」の一例を挙げたい。
先の正育堂書店は、ひばりが丘のパルコにもつい最近まで入っていた(現在は撤退)。一時は中村橋ほか何店か支店があったが、書店経営はやめてしまったようだ(ビルにその名があるが)。ことほどさように、書店は儲からないということなのだろう。ひばりヶ丘駅周辺の書店はパルコの書店1軒のみになった。
その背景を考えるに、本や雑誌はスマホに負けた、という側面は否定できない。わたしたちの「可処分時間」は限られている。もちろん使うお金にも優先順位がある。この意味でスマホの勝利は間違いない。
またネットのタダ情報は雑誌を直撃した。雑誌の定期的な売り上げは書店の経営にとって大きかった。多品種であることが著しく手間のかかる書籍と比べ、雑誌の扱いは比較的ラクだということも経営に寄与していたが、それが大きな打撃を受けた。
書店も90年代あたりから、コンビニ的経営を採り入れていったのだと思う。どういうことかというと、徹底的な「死に筋」の排除である。つまり「売れない」ものは置かず、「この商品は売れています、安心してお買い求めください」という文言が象徴する付和雷同型の消費*への誘導。この結果、書店のコンビニ化、均質化が進んだ。その先には、コンビニと同様の淘汰が待っていたのではないか。いまもこの事態は継続していると思う。
(*松原隆一郎『消費資本主義のゆくえ』ちくま新書、2000年の議論を参照した) 。
紙の本は、レコード盤の復活のように勢いを取り戻すことができるだろうか。
*バックナンバーはこちら⇒
- 書物でめぐる武蔵野 第36回(最終回)
西武池袋線で悪かったな 武蔵野「散歩」主義の試み - 2023年12月28日 - 北多摩戦後クロニクル 第48回
2021年 東久留米駅西口に「ブラック・ジャック」像設置 マンガやアニメでまちおこし - 2023年12月5日 - 書物でめぐる武蔵野 第35回
東久留米の水辺に古代人 身近に潜む意外な「物語」 - 2023年11月23日